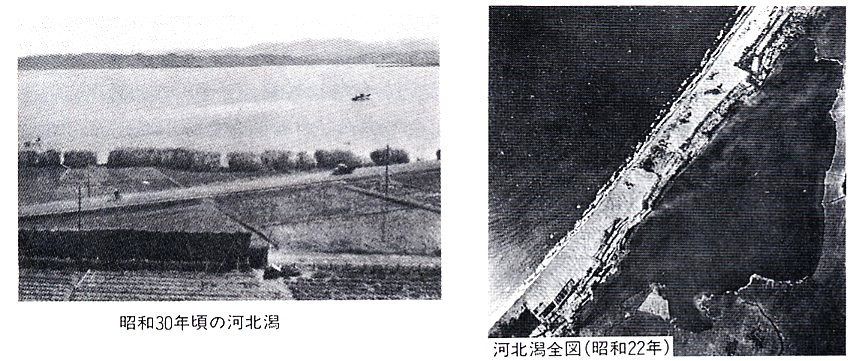
干拓前の河北潟は、日本で20番目(石川県最大)の大きさの湖沼で、水深約2m、周囲35.5km、面積23km2、幅は東西4km、南北10kmあり、浅野川、金腐川、津幡川、森下川、宇ノ気川などが流れこみ、大野川を経て日本海へ排水されていました。(図Ⅰ-1参照)
そのため、満潮時には大野川から海水が河北潟へ流れこみ、塩分を少し含むいわゆる典型的な汽水湖となっていました。干拓後、潟の面積が3分の1となり、防潮水門ができた現在でも基本的にはそれは変わりません。排水口の大野川に近い向粟崎の南西部には、海洋性のアマモが見られ、かつての加賀南部の三湖(柴山潟・今江潟・木場潟)が淡水の沼性であったのに比べると、河北潟は海洋性を帯びているといえます。
したがって、これは魚類に変化を与え、淡水産のものはもちろん、海洋性の魚類(カレイ・キス等)も大野川や湖尻付近に生息するし、河北潟で成長して海へ帰る魚類(スズキやボラ)や海で産卵しまた戻ってくる魚(ウナギ)もいます。河北潟の内水面漁業(以下略して「潟漁」という)はこのために変化を受け、湖岸にある集落の位置によって差異がありました。湖岸には、湖尻の向粟崎から大根布・宮坂・黒津船地内(昭和53年宮坂と合併)・西荒屋・室と六つの漁村が砂丘を背にして並んでいました。潟漁は、年間を通じて営まれましたが、特に秋から冬にかけて本格的に行われていたようです。
昭和20年代で見てみますと、金沢市、内灘村、宇ノ気町、津幡町、森本町に属する湖岸集落(内灘以外では、大野、五郎島、粟ヶ崎、蚊爪、木越、八田、才田、大場、大崎、川尻など)は、ほとんど全部河北潟における漁業権を持っていますが、内灘の6集落と大崎の西岸が、後で見るように漁業権が最も多く、潟漁が盛んでした。なお、東岸では、八田の漁業権が他の集落よりも多く、東岸において特殊な位置を占めています(表Ⅰ-1参照)。
河北潟には現在も淡水魚が数多く生息していますが、その他にも汽水魚や日本海の沿岸魚などが入り交じり、非常に豊富な魚類がこれまで確認されています。『内灘町史』によると、河北潟と大野川で確認された魚は67種ですが、このうちクロダイ・クサフグなど26種は海産魚(沿岸魚)で、ボラなど汽水性魚類が6種で、残り35種が淡水魚です。
主として潟漁の対象となっていた魚介類についてのべると、まず、淡水魚では、キンブナ、ギンブナ、ゲンゴロウブナ、コイ、ワカサギ(内灘ではアマサギ)、シラウオ(内灘ではソメグリないしソメゴリという)、ライギョ(カムルチー)、ウグイ、ウナギ、ドジョウ、ナマズ、ゴリ等があげられます。他に、淡水産のものとして、エビ、アミ(アミ科の甲殻類。エビに似ているが小さい。内灘では、アメグリないしアメゴリという)やカワガニなども獲れました。
また、汽水魚に、ボラ、マハゼ(カワギス)などがあります。魚ではありませんが、汽水湖特有のシジミガイもよくとれました。
最後に、沿岸魚ですが、今日と比べてかなり多く、スズキ、ハネ(スズキの子)、クロダイ、マダイ、シマダイ、イシダイ、サヨリ、トラフグ、クサフグ、マイワシなど多様な海産魚がとれたりしました。特に、ハネはハネ刺網で漁獲されるなど、フナ、アマサギ、ソメグリ、アメグリ等と並んで潟漁の代表的な魚のひとつでした。クロダイ以下の沿岸魚も、底袋網にかかったりしましたが、漁獲量そのものはそれほど多くはありませんでした。それでも、今日想像するよりもはるかに多くの沿岸魚が、満潮時に大野川をさかのぼって河北潟に入り込み、湖岸の漁民の食卓をにぎわせたり、あるいは出荷されたり、振り売り(行商)されたりして貴重な収入源となっていました。
昭和20年代頃までの河北潟は、水もかなりきれいで、これらの魚たちが生息するのに十分な条件を満たしていたといっても過言ではないでしょう。
漁業の村、内灘にとって、かつて大きな比重を持っていた潟漁およびその漁業権についてのべてみましょう。
河北潟の水面は沿岸の村(図Ⅰ-1参照)によって分割所有されることなく(これは、全国的に非常に珍しい)、誰でも自由に使用できましたが、そこで漁業を行う場合にのみ漁業権の制約を受けます。明確なことはわかりませんが、漁業権はかなり古い時代からあったようです。
水田農業に力を入れている東岸から南岸の集落は、八田を除いて、潟漁をそれほど重視しなかったようですが、一方農業をほとんど行わず、生活の基盤を漁業に依存していた内灘村にとって、潟漁は極めて重要なものでした。
(明治末期頃までの話ですが、浜漁のみに依存していた金石、大野、七塚等では、海が10日以上もシケるとたいへんこまったといいます。潟漁を併せ行っている内灘の場合は、それほどでもなかったようです。当時の潟漁の重要性がうかがわれます)
さらに潟漁に関してですが、藩政期以来、明治の中頃に漁業出稼ぎを行うようになるまでの間に、漁業権についてかなり多くの紛争がありました。明治以後にも2、3あったようですし、古くは幕末の豪商銭屋五兵衛が河北潟を埋め立てしようとして、内灘(向粟崎・大根布・宮坂など)をはじめとした湖岸漁民の激しい反対にあい失敗した大紛争(いわゆる「銭五事件」)が知られています。このような点からすれば、砂丘地に立地する内灘の漁民にとって、古くから、潟漁は生活を支える重要な手段であったと推定できます。
現在知られている、成文化した「漁業権に関する規定」の最も古いものは、文化2年(1805)8月に制定された『河北郡内潟・猟業相用候網員数長短並役銀取立方定』です。「猟」とは漁のことであり、これによって各集落の漁法、すなわち網の数と大きさおよび漁業場所と漁期が定められ、あわせて厳重な刑罰が付記されていました。これは、不完全なものでしたから明治10年(1877)に従来から存在した不文律・習慣等を総合して「河北潟漁業営業上漁具或いは季節等制限のこと*」が定められました。 これは、前記の文化2年に定められた精神をそのままにしたといってよいほどの漁業規約です。さらにその後「漁業組合法」(明治22年)や「漁業協同組合法」(昭和24年)が制定され、この規約は多少の変化をしたのにもかかわらず、その精神はつい最近まで続いていました。
* 河北潟における定置網漁業権(底袋網)は、この法令以前は、向粟崎が独占していました。また、明治24年以後、ウナギ袋網以外は、他の集落にも大幅に認められるようになりました。
戦後になって、昭和24年漁業法が改正されましたが、その最も大きな改正点は、農業における地主的存在にも似た定置漁業権の廃止です。その廃止後、この定置漁業権を含めた他のすべての漁業権は、湖岸の9組合から選出された運営委員会が、毎年組合員より提出された希望を、基本の漁業権に基づき、魚の保護その他を考慮して割り当てました。この割当てを左右するのは主として各組合の連合会への出資金と、稚魚(ウナギ・アマサギ・コイ等)放流の分担金の割合によることが多いようです。表Ⅰ-1に示したものは、各組合の基本漁業権と昭和29年度の割当てです。
河北潟の内水面漁業は、基本漁業権が示すように、各組合(各集落)によってそれぞれ特色がありました。たとえば、シジミガイは木越など河北潟南部のみの権利であったり、ウナギの漁業はほとんど向粟崎の権利になっていたことなどです。昭和30年頃、権利の最も多かったのは、向粟崎と内灘中央(大根布・黒津船地内・宮坂)で、次いで内灘北部(西荒屋・室)、大崎および湖東の八田と河北潟南部であり、才田・川尻・大野は最も少なかったのです。(15頁の表Ⅰ-1参照)
このように各集落によって潟漁が異なるのは、すでにのべたようにその地区の立地条件(湖東は稲作を中心とした農村であり、湖西は砂丘に立地する)によるわけですが、さらに内灘の場合は、出稼ぎに行くのがカイ場(猿払のホタテガイ漁場)であるかニシン場(主として羽幌)であるか、あるいは浜漁業に力を入れているか否かによっても異なっています。一例をいえば、昭和20年代の初め、向粟崎は、出稼ぎでは毎年ほとんど(ある年では全員)カイ場なのですが、これは春先のイワシと初夏のサバ漁を地先で行うためであり、定置網漁業(底袋網)を中心とした潟漁にも力を入れていた、いわば地元漁業中心の集落だったからです。こうしたことは、集落が湖尻近くにあって、潟漁も浜漁も行うのに便利な所に立地するからと思われます。
昭和25、6年頃までの内灘の各集落では、長い冬が終わって3月の声を聞くようになると、ニシン場の出稼ぎの準備で忙しくなったといいます(主に向粟崎・大根布・西荒屋・室)。一方、浜漁を行う人は、その準備にかかりました。
春の潟漁は静かに行われます。フナは産卵のために潟から河川へ上り始めます。初夏になると砂丘の農繁期がやってきますが、麦の刈り入れは刈るのではなく引き抜く簡単な作業ですし、麦のうねの間にはサツマイモの苗が植えられます。湖(潟)の西岸にあるわずかの水田は、田植えが終わった蚊爪・木越・八田など東岸の人々をやとって田植えされます。夏が近づくとハネが、海から大野川をさかのぼってきます。初夏には主にアメグリ漁業だけが、短い漁期を利用して行われます。これは、腐敗が早いので、一度熱湯を通したもの(しぼって一晩ムシロの上でさっと乾かす)を、金沢を中心に振り売りされます。夏が終わる頃には、フナは川から潟へ下っています。秋になるにつれコイ・ゴリ・アマサギ・カワギス・ボラ等の漁期が始まり、シジミガイの肉もついてきます。
全体を通じて、産額の多いのは、フナ・アマサギ・ハネ・シジミガイ等でした。魚類と網の関係は次のようです(昭和30年頃)。
|
袋網・・・・・・・ |
フナ・カワギス・ウナギ・ハネ・アユ・ボラ・ウグイ・カワガニ ボラ・フナ・エビ・ゴリ・ウナギ・カワギス フナ・ナマズ・カワギス・コイ・ゴリ・エビ・サケ・ボラ フナ・ナマズ・ゴリ・エビ・ウナギ 網ゴリ ゴリ・アマサギ・フナ・ハネ ソメグリ(シラウオ) アメグリ アマサギ カワギス ボラ・フナ・コイ・ハネ エビ |
これらの網の名称は、漁業権に示されたものと異なるものがあり、集落によっても呼び方が違っています。
魚種別・組合別の水揚げ高は、表Ⅰ-1のようになります。この表で注意しなければいけないのは、内灘中央漁業組合のもので、水揚げ高(量)に比べて産額(金額)が少ないのは、ここの水揚げ高の半分を占めるアマサギが1~2寸(3.3~6.6cm)くらいの時に獲るため値段が安く、他の組合の方は4~5寸(13.2-16.5cm)の大きいものを獲り(網の種類が異なるため)、2~3倍の値段となったからです。
月別の水揚げ高および産額の正確な数字はつかめませんが、毎年10月にピークが現れ、次いで多いのは1月と7月です。10月と1月は冬のもので*、7月はアメグリとウナギです。
* 少し前まで、金沢地方では正月にフナを食べる風習が残っていました。タイは食べなくてもフナやブリを食べないと正月の気分がしないとさえいわれました。したがって、12月末から1月にかけてフナはいつもよりも多く獲られ、統計には1月に現れることになります。
魚の販路
潟で獲れた魚の販路は、大部分が金沢です。漁業組合の手を経ずに振り売りされる量も相当多いことは確かでした(当時の組合の人の話では、約6割ほど)。
かつて大根布の婦人は、「根布のイタダキ」(頭上運搬;巻頭写真参照)と称して、金沢を中心にさかんに振り売りに歩きましたが*、コレラなどの病気が原因で、その慣習も大正5年頃で終わり、その後は、ざる・ブリキ箱などを背負ったり、リヤカーを引いたりして金沢などの各家庭を訪問販売していました(それぞれ、得意先を持っていました)。なお、組合を通したものは、金沢の魚市場へ売られました。
* 振り売りの範囲は、主として大根布(向粟崎も少しいた)の婦人によって拡げられ、最盛期は、金沢・河北郡はもちろんのこと、富山県の砺波地方から鶴来・美川方面にまで出かけたといわれています。
大正元年(1911)の資料でみますと、潟漁を営む全漁業者の数は1608人で、うち内灘の漁民は600人です(約37パーセントを占める)。このうち内灘で操業する漁法は8種類で、種類は少ないのですが免許権の数は多く、潟漁を営む地区のなかでもたいへん特色ある地区となっています(表Ⅰ-2参照)。
この表からも明らかなように、内灘独自の漁具として、船曳網(100%;後述するいわゆる狩曳のこと)、底袋網(96.9%)があり、他に多い漁具としてカワギス刺網(69.6%)、小網(50.2%)などがありました。
漁法や漁具には地域的特色があり、しかも変遷があったものの、この頃、内灘各地区の代表的な漁法として、
向粟崎の底袋網
大根布の狩曳(船曳網)、
宮坂の桁曳(小網)、
向粟崎、西荒屋・室の投網(巻打ち)
が、ありました。以下、大正期から昭和初期における潟漁について地区別にのべることにしましょう。
明治22年(1889)の「漁業組合規約」にきる制限漁法は、底袋網・投網・カワギス刺網・持網・小網(ただし一部にソメグリ網・アメグリ網・エビ網が認められる)があげられています。
向粟崎の代表的漁業は、底袋網(いわゆるフクロアミ)です。これは大野川や潟のある一定の場所にしかけるいわばミニ定置網漁法で、袋の中へ入り込んだ魚は逃げ出せませんから、網をあげる時以外は傍にいる必要がなく、同時にいくつかの網がおろせ、省力化もできるようになりました。海から上がってくるキスやシマダイなどの海洋性の魚はもちろんのこと、河北潟で成長して海へ帰るスズキやボラ、海で産卵してまた戻ってくるウナギなどを、底袋網(ミニ定置網)で効率的に獲ることができました。当然、漁獲量が安定していましたので、向粟崎は、潟漁を営む上で非常に恵まれた地区であったといえます(したがって、向粟崎は、他の地区ほど出稼ぎ一辺倒ではなかったようです)。この底袋網は資産のある漁家が多数所有し、一般の漁家は投網漁が主でした。
漁場に設置された袋網は、1日に10数個まで交換しました。網は綿糸で、使用後は網干場で乾燥する必要がありました。このため一家で、ゴリ網とボラ、フナの両方合わせて100個~200個ばかりの底袋網を所有していたとのことです。
向粟崎地区は上出・中出・下出に3分され(これらは漁業組織上の「組」ともなった)、それぞれの湖岸に袋網漁場がありました。網場は岸より沖へ1番から5番まであり、各組は、くじびきで順番を決めて網を設置し、3日ごとに場所交替するきまりをとっていました。また、組の内部でも右岸から左岸へと位置を交替させて、各家が均等に網の位置がふり分けられるよう工夫していました。
投網はたくさんの舟で行う巻打ち漁法というやり方で、約30艘の舟が組になり、2列に向かいあって進み、外側から内側へと1艘の舟が2網ずつ投網を打って近づけていく漁法をとっています(図Ⅰ-6参照)。この漁法については、西荒屋・室地区のところでその都度説明することにします。
大正期の向粟崎では、袋網漁と持網漁(いわゆる四ツ手網のこと)、そして投網の巻打ち漁が主でした。北海道などへの出稼ぎが開始されるようになると、向粟崎地区における潟漁は、出稼ぎに出ない人により主に冬期間行われました。投網は9月から12月、袋網は9月から翌年のイワシ刺網漁が始まる頃(9月末頃)まで行われました。
向粟崎の潟漁で獲れた魚は、袋網ではフナ(ゲンゴロウブナ)、ウナギ、ボラ、カワギス、ライギョ、ゴリなどで、投網(巻打ち漁法)では主にフナとボラを漁獲しました。
明治22年の「漁業組合規約」によると、シロゴリ(ソメグリ)網、投網、アメグリ網、小網、カワギス刺網、エビ網、持網、根掛杪漬の8種が許可されています。大正から昭和初期においては、狩曳という漁法が主に行われていました。これは、8月末から翌年の3月末頃まで潟の全域を範囲に行うもので、大根布地区独特の漁法です。
舟2艘が1組となり、舟1艘に2人が乗り込みます。そして1艘が長さ11ヒロ(19.8m)ほどの綿糸で作った布袋の重網をおろし、他の1艘が長さ28ヒロほど(約50m)の口網をおろしながら、同じ位置から同時に始めて、円を描くように狩り込むものです。2艘の舟は1日交替で重網と口網を受け持ち、このような組が最盛期には大根布だけで50組を数えたといいます。重網は主として金沢の漁網屋から購入しましたが、明治末年までは、麻糸によりをかけ自分でつむいで自製したととも伝えられます。
8月末から11月頃までソメグリ(シラウオ)・ゴリ・ハネ・アマサギ(ワカサギ)を対象に主に布網を使い、12月から翌年3月までフナ・アマサギを対象にイチ網(荒目の網)を用いたため2種類の網が必要でした。網は舟を持っている家はほとんど所持していますが、2人1組なので、相手が舟子(かこ)の場合もあり、また子供を使う場合もあって、その狩曳組の事情によっては共同で所持することもありました。
狩曳は朝出かけて晩に帰るまでの間に25~30回の網の揚げおろしがあったといいますから、かなりの重労働だったといえましょう(狩曳の仕事はせいぜい35歳ぐらいまででした)。特に夏の間に小学校3年から上の子どもを使うことがよくありました。これは大人がほとんど出稼ぎに出ている関係からで、大根布の場合、男子は早くから漁師になることが仕込まれたといえます。
漁獲の分配は1艘ずつ等分され、さらに舟子を使った場合、舟と網が船主持ちですので、舟子は3分の1、船主は3分の2をとりました。狩曳の漁場の選定は難しく、アマサギ、ソメグリなどは潟の風向きと潮の流れの影響を受けやすく、特に風の強い日の後の水の濁りなどが考慮されました。
他に大根布ではスズキの子のハネを獲る「ハネ網」がありました。これは麻を紡いで自製したもので、高さが約5尺(150センチ)ほどあり、風の強い日には藁2本で下の部分を結んで用います。主に川尻から八田前に至る潟の東岸の藻の中のハネを6月末から8月末頃までの夏季間に獲ったわけです。これは、主に出稼ぎに行かない年寄り漁師の仕事とされました。
また、垣網(かきあみ)という刺網が大根布で15~16把使われました。これも潟の東岸のヨシ(葦)の生えている縁や藻縁(もぶち)に25~30ヒロ(1ヒロは約1.8m)の長さで、7~8節の網目の垣網を夜間にしかけ、朝あげるというものです。さらに手なぐさみ程度の小規模な漁法には、ツキダシタモが行われました。これは同じくヨシの生えた入口に舟を寄せ、舟のトモ(図Ⅳ-2参照)からタモを静かにおろし、棹などを使って、ヨシの間聞から狩り出したフナを獲るやり方です(この漁法をトッポンという)。
その他、狩曳によく似たやり方で舟1艘を使って行う「ウナギ曳網」や「ボラの流し刺網」や「アメグリ網」、「アマサギ網」、「底袋網」などの漁法が行われていました。
明治22年の「漁業組合規約」によれば、旧黒津船地内では、小網、カワギス刺網、投網、アメグリ網、エビ網、根掛杪漬(つけぼえ)の6種が、そして宮坂では小網、投網、アメグリ網、エビ網、カワギス刺網、根掛杪漬の6種が許可されていました。
宮坂の主流は小網(小桁網)で俗に桁曳(けたびき)といいました。桁曳は1艘につき3人乗り込み、櫓と櫂2枚からなり、マエフリ、ウシロフリがありました。
小桁網こげたあみ(桁曳)は樫の木で造られた桁に石のおもりを2個左右につけ、袋状の網をその後につけて、潟底を曳くもので、網漁でも古い形態の漁法です。宮坂では3種の曳網が使用され潟の中央で曳くコゲタ網は、底の泥が柔らかいので曳きやすく、オオゲタ網は岸の近く藻の中を曳くので、網目も細かいのが特徴です。チュウゲタ網はその中間の網です。冬期間の潟のフナは底魚なので、沖に出てから風の具合を見ながら判断し、3種の網を使い分けました。
桁網は1艘一つ曳きで、網を下ろすときは1人で、あげるときは1人か2人でしますが、風のあるときは3人でかかることもありました。また、オオゲタ網を使うことも多かったようです。桁曳は小網(小桁網)をひいて藻の中のフナを獲るもので、天候や水温の加減で魚の移動があり、漁場の選定もたいへん難しかったようです。
他に9月~10月にかけてカワギス刺網漁がありますが、これは潟の岸近くのかたい泥とやわらかい泥の中間のヒプチと称される所に竹をさし、長さ20ヒロ(約36m)、高さ2ヒロ(約3.6m)の刺網を4統かけました。これは、出稼ぎに行かない年寄りの仕事で、夕方しかけ、翌朝、あげに行きました。また6月頃にはアメグリ網漁が行われましたが、この時使用された網は綿糸の袋網からできていました。 その他に、フシを取った何本かの竹筒を紐でしばって潟の底に沈め、ウナギが入った頃を見計らって静かにあげる、いわゆる「竹筒漁法」(内灘ではタンポポという)も、宮坂や大根布で行われていました。
明治22年の「漁業組合規約」には、投網、小網、アメグリ網、カワギス刺網、根掛杪漬の5種が許可されていました。
主な漁法は投網の巻打ちで、西荒屋では14歳で投網に出たといいます。これは、藩政時代よりフナ、ボラなどを獲るために行われていた漁法で、まず小舟に2人が1組となって乗り込みます。これをトモサシデといい(1人は舟のトモで櫓をこぎ、他の1人が舟のオモテから投網を打つ)、最初200mぐらいのところからお互いに魚を追いながら魚を囲んでいきます。そして、40艘の舟が図のようにそれぞれ20艘ずつ2列に並び、「ヤルゾー」の号令に合わせて、一勢に内側に向って網を打ったわけです。潟漁は、どんな場合でも技術や技能が必要なのですが、特にこの巻打ち漁法は、個人(投網をする人)の技術を必要としました。4月から6月頃にかけて主に行われました。
風の強い日は巻打ちができないのでボラの流し網かカワギスの刺網をしました。この場合は、ヨシの生えた縁で、1人で舟を操り、アンカ(イカリ)を底におろして100ヒロ(約180m)の縄を引っ張りました。舟は板船といって(略してイタネともいいます)、各地区ごとに少しずつ材料が違っていたようです。板船に乗る人数は、西荒屋の場合、明治期までは1艘に3人が乗り込んだこともあったようですが、大正期には2人に、昭和5年頃には一人乗りへと変化しました。、
他に「桁網」(小網)と「ツケボエ」(俗にいう根掛杪漬漁)があり、アマサギ・ハネ・ボラの刺網やソメグリなどの袋網が行われました。ツケボエは許可制で、西荒屋全体で20個ほどですが、主に西荒屋前の潟でホエ(木偏に少)束を沈め、頃を見計らってホエを浮かし、巻網・投網で捕獲するもので、ムラでは約10戸の家で行っていました。
明治22年の「漁業組合規約」には、投網、小網、アメグリ網、カワギス刺網、根掛杪漬の5種が許可されていました。室の主要な潟漁は、投網・小網(小桁網)・ツケボエ(根掛杪漬)でした。投網は、潟では向粟崎・西荒屋・室・大崎(宇ノ気町)が主流で、いずれも巻打ち漁です。
投網巻打ち漁は、室でも他の地区と同様に、10艘から15艘の舟が並んで進み、舟の影でボラやフナを内側に追い込みます。舟は八の字型に進み、途中左右の列が交差し先頭の舟から順に投網を打ちます。次に先頭の舟は最後尾に列を変えます。このようにして投網巻打ち漁を行っていくのですが、一般に真ん中の舟が最もよく獲れたといいます。主に11月から12月が最盛期で、1日にフナをザルに3~4杯漁獲することもよくあったそうです。
投網は12~13ヒロ(1ヒロは約1.8m)の麻製テナワにレンゾウ、コシ、ツマゲと称する3段に分かれた網によって作られていて(図Ⅰ-7参照)、ツマゲ部分は綿糸網で、その他は麻糸の網からできていました。麻糸は年寄りの婆さんが糸車で紡いだ糸を網針で編んでつくったといいます。
投網の打ち方は、テナワから順番に巻いて自分の手前の網を少したぐり寄せ、ツマゲの裾を平均に揃えて左手前から外へ一度出し、次に左腰の後方にさげて反動をつけ、空中で広げて投げるといわれています。投網を打った後、水が濁るのですぐに小網(小桁網)をおろして残りの魚を獲ることもありました。
また、冬期水が冷たい時、フナなどは底の泥にねむっているので、桁網(小網)を使って獲ったりしました。岸近くには藻があるので、藻の間のフナはオオゲタ網を使用して漁獲しました。桁網はムラの大工に桁を作ってもらい、自分で石を拾ってきて重さを計りながら左右均等にし、形の悪い石は布で包んで取りつけました。
桁につけた石をオモシといい、3本の縄はケタナワと呼びました。真ん中のケタナワを、特に引っ張ったり、ゆるくしたりして加減し、袋の角度を勘で調節しました。袋の角度によって、曳きが重くなったり軽くなったりするからです。袋状の端にはイオダマリがあり、魚を取り出す口をしばるシリソがついていました。